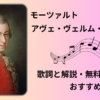バッハ「主よ、人の望みの喜びよ」【解説とyoutube動画】
目次
バッハ「主よ、人の望みの喜びよ」の解説
「主よ、人の望みの喜びよ」はドイツの作曲家、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685-1750)が作曲した教会カンタータ『心と口と行いと生活で』(独:Herz und Mund und Tat und Leben)BWV147の第10曲(終曲)です。(※第6曲でも同じ旋律が用いられています。)
教会カンタータはプロテスタントの教会で礼拝用に作曲された器楽伴奏付きの声楽作品です。
1723年の作とされるこの大変有名な曲は単独で演奏されることが多く、オルガンをはじめ様々な楽器用に編曲され広く親しまれています。
カンタータ『心と口と行いと生活で』
まずはオリジナルのカンタータをご紹介しようと思います。作品はアリアとレチタティーヴォ、合唱の10曲から成っています。
アリアは国によって若干ニュアンスの違いがありますが、広義には叙情的、旋律的な特徴の強い独唱曲のことを指し、オペラの中でもよく登場しますが、カンタータの中にも含まれます。
「G線上のアリア」として有名なバッハの管弦楽組曲第3番のアリア(仏:Air)のように器楽曲を示す場合もあります。
レチタティーヴォは話し言葉で語るように歌われる独唱を指し、アリアが旋律的な特徴が強いのに対し、レチタティーヴォは劇の状況や物語の展開を説明するシーンで用いられます。
バッハ カンタータ『心と口と行いと生活で』BWV147
第1部
第1曲 合唱「心と口と行いと生活で」(00:27)
第2曲 レチタティーヴォ「祝福されし口よ」(04:30)
第3曲 アリア「おお魂よ、恥ずることなかれ」(06:15)
第4曲 レチタティーヴォ「頑ななる心は権力者を盲目にし、最高者の腕を王座より突き落とす」(09:55)
第5曲 アリア「イエスよ、道をつくり給え」(11:35)
第6曲 コラール合唱「イエスはわたしのもの」(16:20)
第2部
第7曲 アリア「助け給え、イエスよ」(19:00)
第8曲 レチタティーヴォ「全能にして奇跡なる御手は」(22:45)
第9曲 アリア「われは歌わんイエスの御傷」(25:15)
第10曲 コラール合唱「イエスは変わらざるわが喜び」(27:55)
Philipp von Steinaecker指揮 Musica Saeculorum
ソプラノ:Anna Dennis
ソプラノ: Charmian Bedford
アルト: Owen Willetts
テノール:Andrew Tortise
バス:Jonathan Brown
バッハ「主よ、人の望みの喜びよ」のyoutube動画
ここでは様々な楽器用に編曲された演奏を聴いてみたいと思います。
最初にご紹介するのは独唱と合唱による演奏です。
バッハ:主よ、人の望みの喜びよ(コーラス版)
Bel Canto Choir Vilnius
次にご紹介するのは2台のピアノのために編曲された版での演奏です。
ピアノならではの静謐な感じが心を落ち着かせます。
バッハ:主よ、人の望みの喜びよ(2台のピアノ版)
ピアノ:Lucas & Arthur Jussen
次にご紹介するのは比較的聴く機会の多いオルガンでの演奏です。
宗教曲はやはり教会の独特の残響の中で聴くのが雰囲気があって良いですね。
バッハ:主よ、人の望みの喜びよ(オルガン版)
オルガン:Willem van Twillert
最後にご紹介するのはチェロの独奏とオーケストラ、合唱による演奏です。
バッハ:主よ、人の望みの喜びよ(チェロ版)
Elisabeth Fuchs指揮 Zagreb Philharmonic Orchestra
チェロ:ステファン・ハウザー
いかがでしたか?こちらの作品もぜひ聴いてみてください!
お役に立ちましたらクリックをお願いします。
参考資料:「心と口と行いと生活で」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』2020年3月8日 (日) 04:41 URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/心と口と行いと生活で